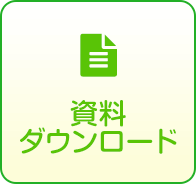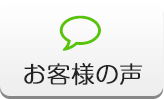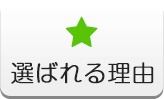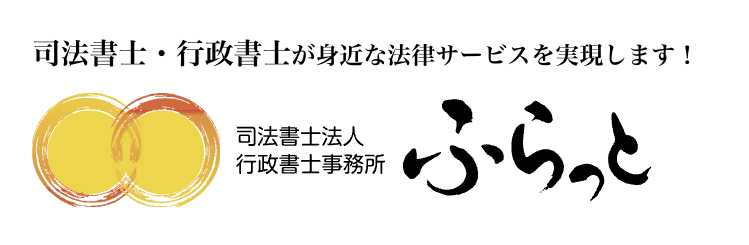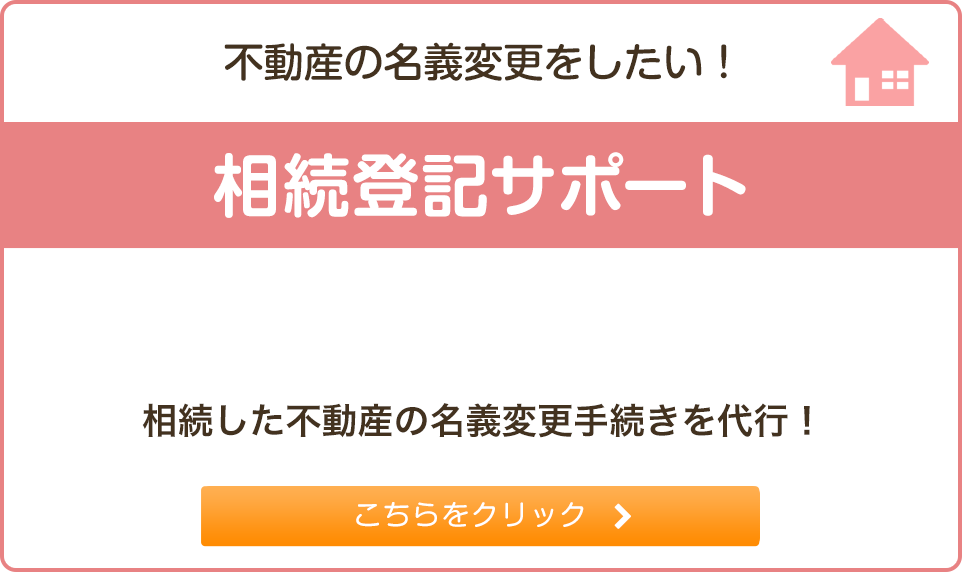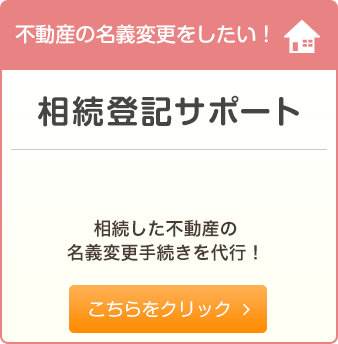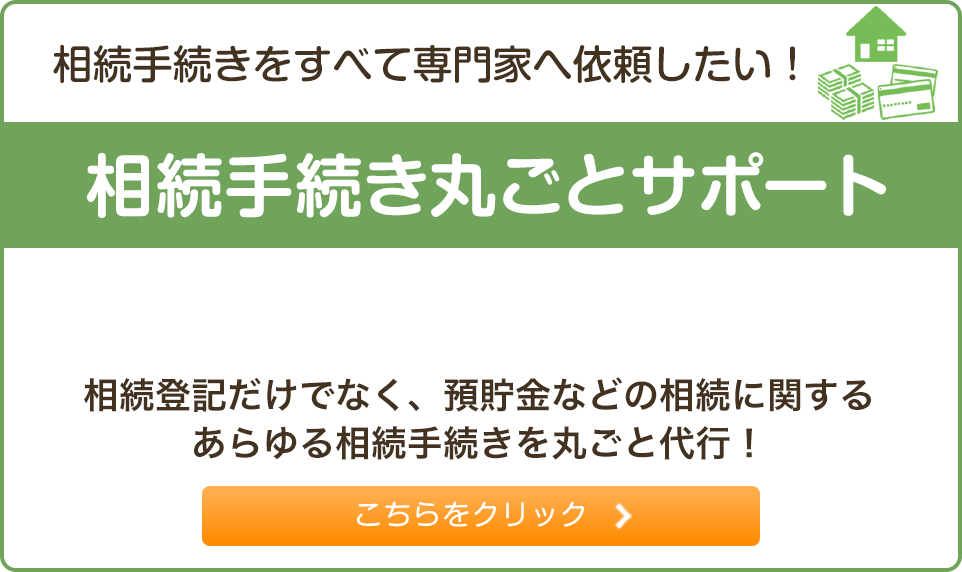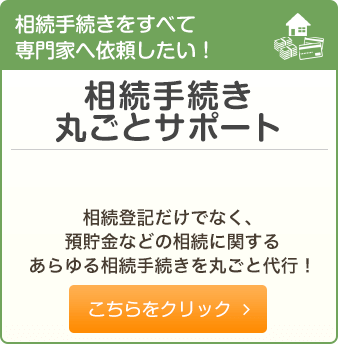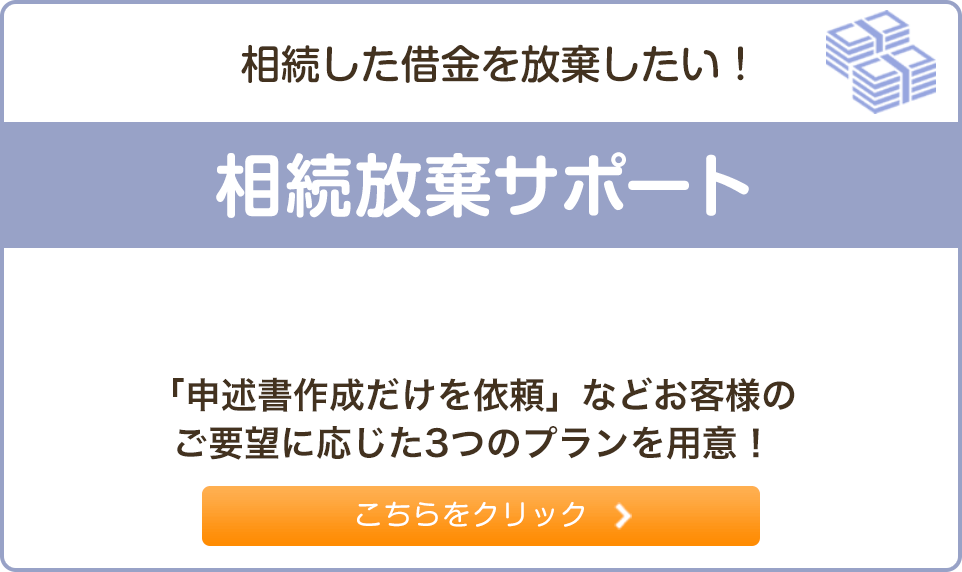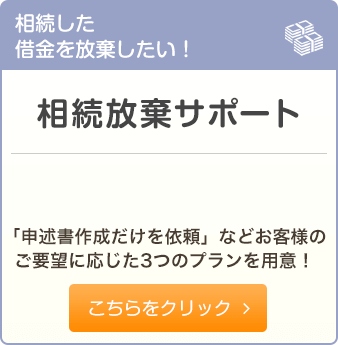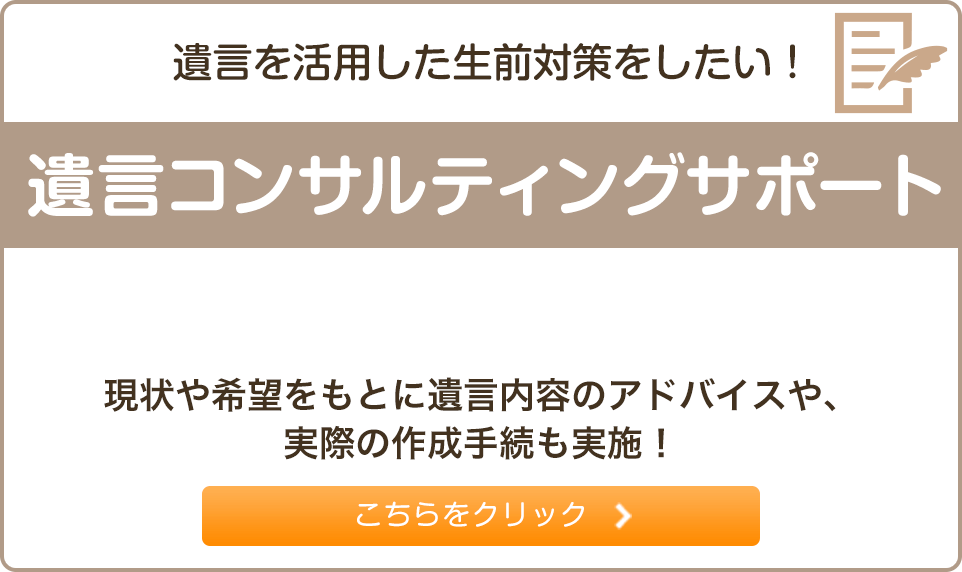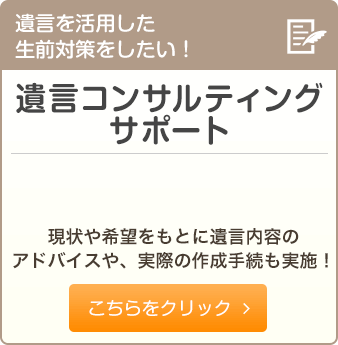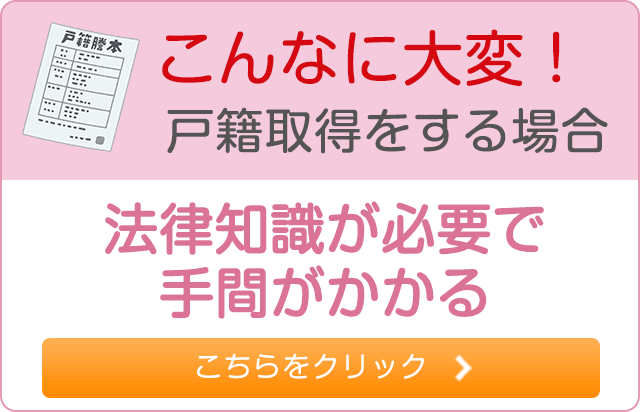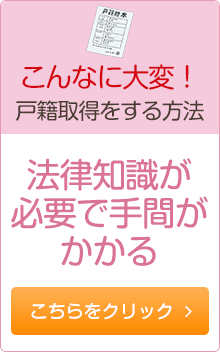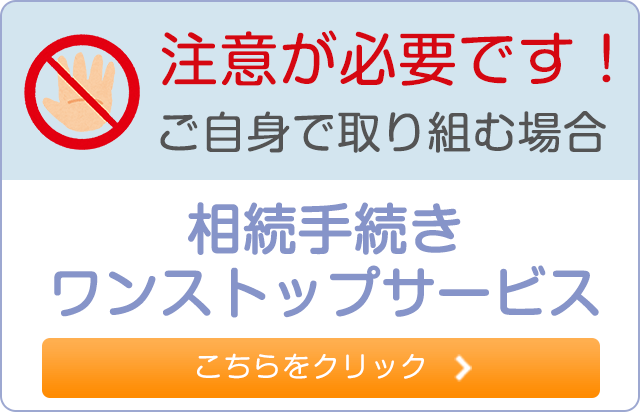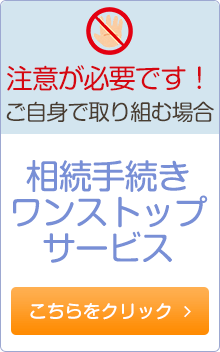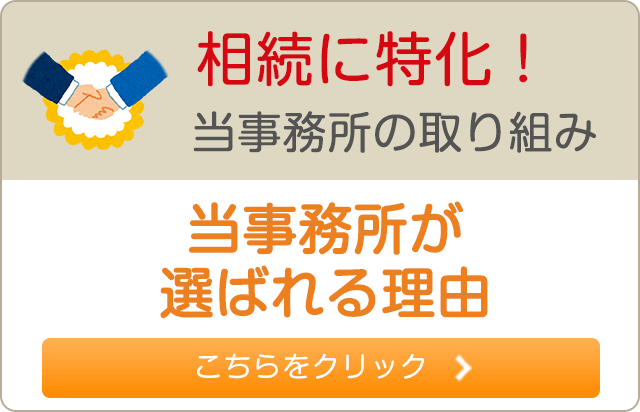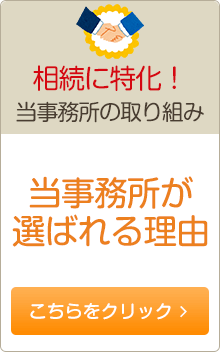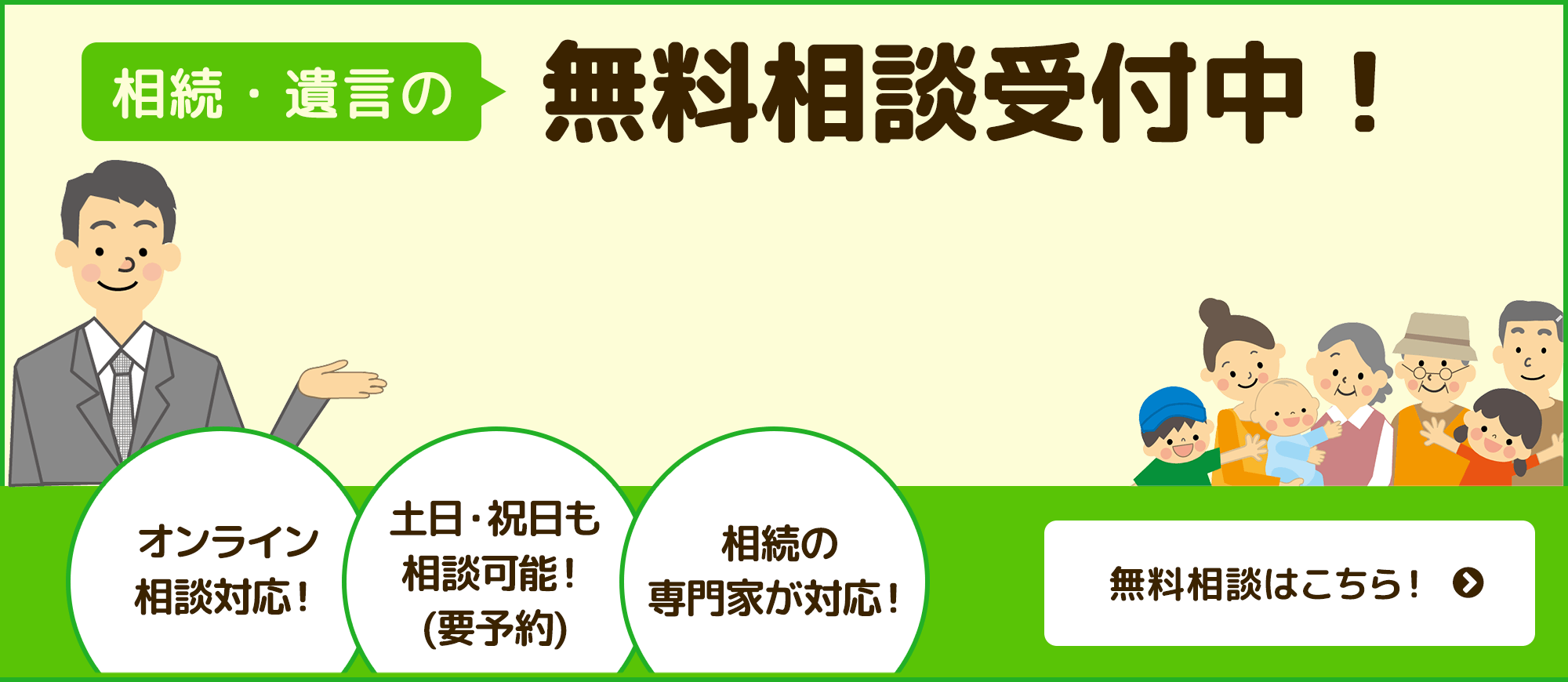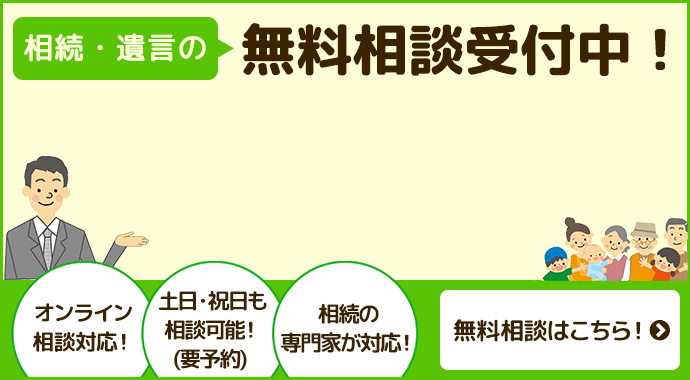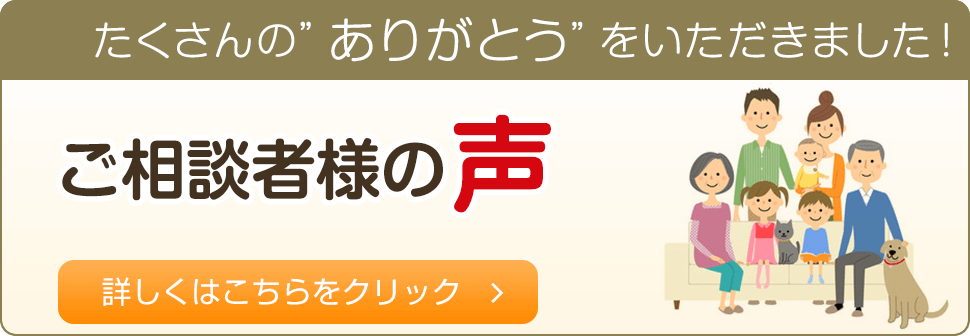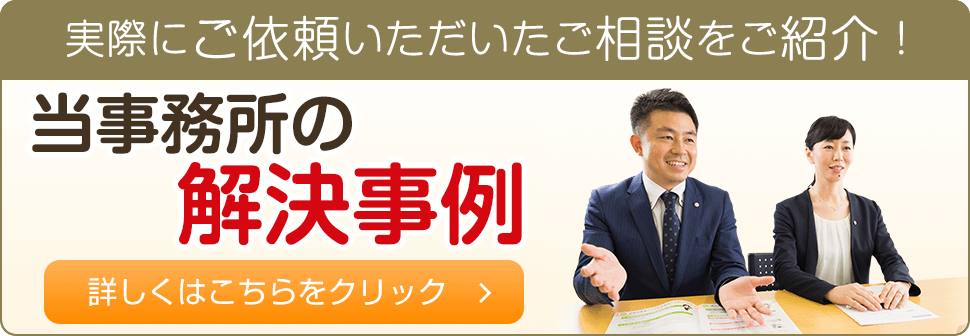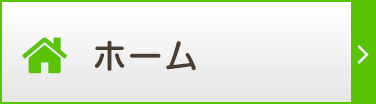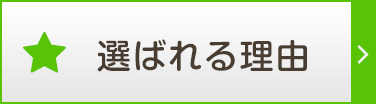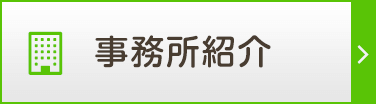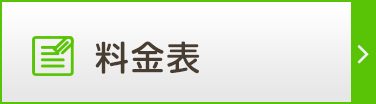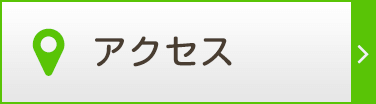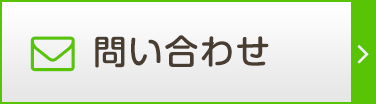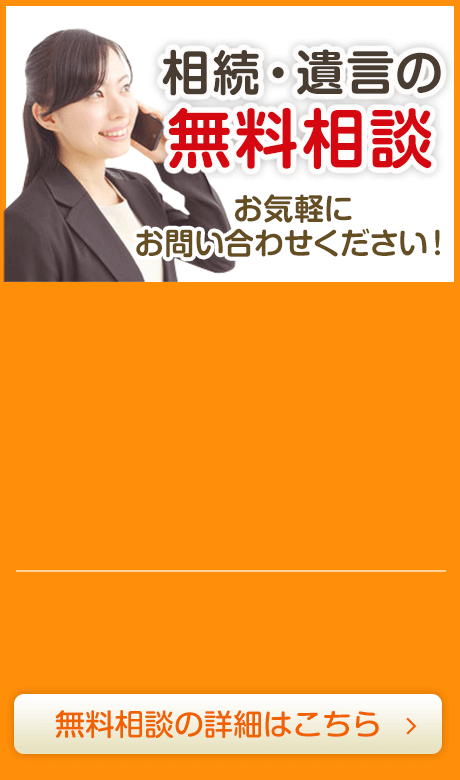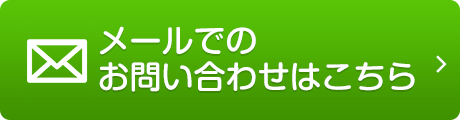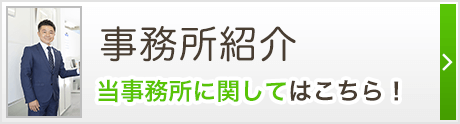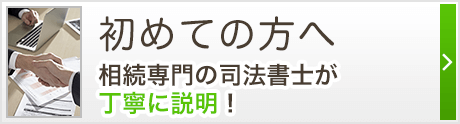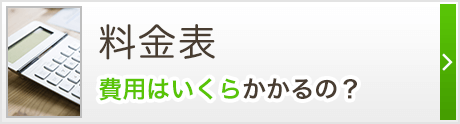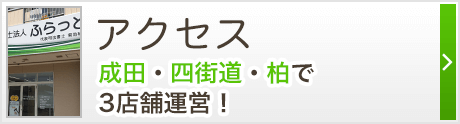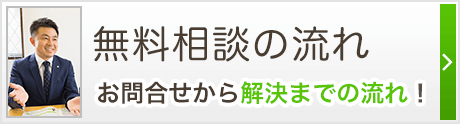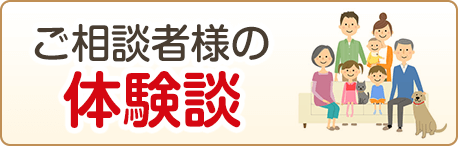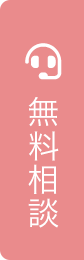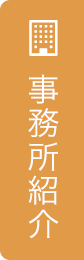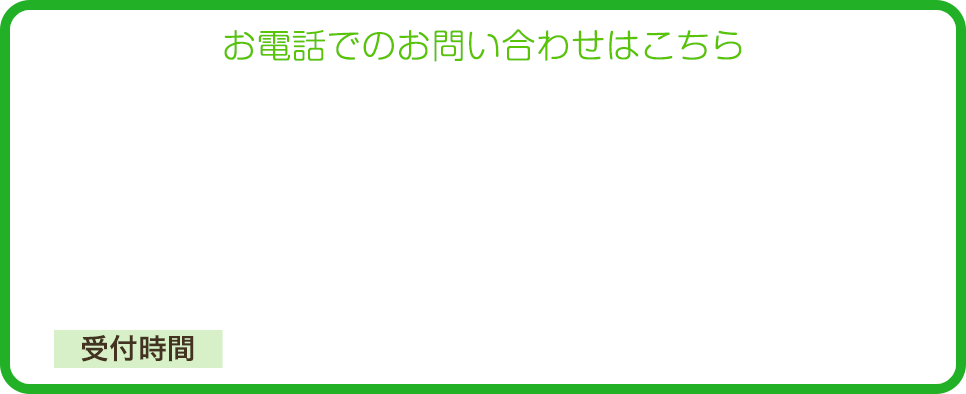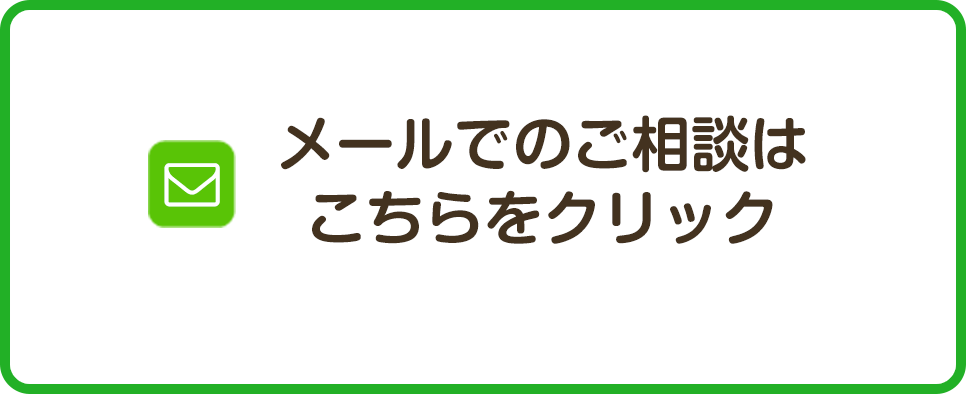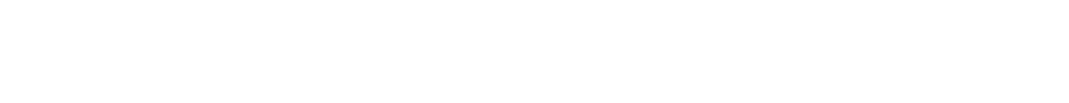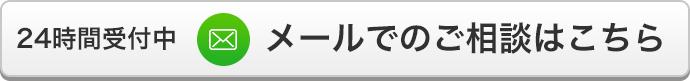崖地の相続税評価の方法と買取の注意点を徹底解説
相続した土地に急な斜面(いわゆる「崖地」)が含まれている場合、その評価方法に頭を悩ませる方は少なくありません。通常の平坦な土地と異なり、崖地を含む宅地は利用上の制約が大きいため、相続税評価にも特別な取り扱いがあります。こちらのページでは「崖地の評価」と「崖地の買取」に焦点を当て、崖地とは何かという基本から相続税評価の具体的な計算方法、評価時の注意点、誤解しやすいポイントや売却時の課題まで解説しますので、相続人の方や崖地をお持ちで評価に不安がある不動産所有者の方はぜひ参考にしてください。
目次
崖地とは何か?法的定義と日常的なイメージ

「崖地」とはどのような土地を指すのでしょうか。一般的には傾斜角度が30度以上の急斜面部分を含む土地のことを言います。傾斜が緩やかな場合(30度未満)は原則として税法上は崖地とはみなされず、代わりに「利用価値が著しく低下している宅地」として一律に10%評価減(評価額を1割減額)などの措置を検討するのが実務です。つまり、傾斜の程度によって適用される評価減のルールが異なることに注意が必要です。
なお、「崖地」という言葉自体は法律上の厳密な定義があるわけではありませんが、財産評価基本通達(相続税評価の指針)において30度以上の急傾斜地を含む宅地を評価する特例として「がけ地補正」が認められています。日常的なイメージとしては、山裾や台地の縁を造成して宅地にした結果、一部が崖状になっている土地、あるいは宅地と隣接する部分に高さのある擁壁や崖が存在する土地が該当します。登記簿や公図上で「宅地」として一筆の土地でも、その中に急斜面部分がある場合は崖地に該当し得ます。実際、住宅地造成が行われた地域では、平坦な敷地の裏手や隣地との境界付近に高さ数メートルの崖(擁壁を含む)を有する宅地は珍しくありません。こうした崖部分は傾斜が急で建物を建てることができず、通常の利用が難しいため、相続税評価上も考慮が必要になります。
崖地の相続税評価方法:がけ地補正率による減額

崖地を含む宅地の相続税評価には、通常の評価方法に加えて「がけ地補正率」と呼ばれる補正(減額)が適用できます。国税庁の財産評価基本通達に基づき、評価計算式は以下のようになります。
- 通常の評価額(もし崖部分がないものとみなした場合の評価額)に、がけ地補正率を乗じて計算した価額を最終的な評価額とする。
まず崖地を含む土地を「平坦な土地だったらいくらになるか」を算出し、そこに所定の補正率(がけ地補正率)を掛けて評価額を減じる仕組みです。このがけ地補正率は、その土地に占める崖部分の面積割合(=崖地地積/総地積)と崖の斜面の向き(方位)によって決定されます。具体的な計算手順は次のとおりです。
- 崖部分の割合を算出:崖地部分の面積を土地全体の面積で割り、「崖地割合」を求めます。
- 崖の向きを判定:崖がどの方角を向いているか(北・東・南・西)を確認します。崖の方位とは、斜面そのものが向いている方向のことです。例えば敷地内の崖が北方向に面していれば「方位:北」の崖と判定します(※崖が真東・真西などではなく北西や南南東など中間的な場合は、該当する2方位の中間値を用いるか、近い方位に読み替えて扱います)。
- 補正率を適用:国税庁が定める「がけ地補正率表」に従い、崖地割合と崖の向きに応じた補正率を選定します。補正率表では、崖地割合が大きいほど、また崖の向きによっては補正率が小さく(評価減が大きく)設定されています。たとえば、崖地部分が全体の25%(崖地割合0.25)の場合、崖の方位が南なら補正率0.92、方位が北なら補正率0.88となります。同じ面積割合でも北向きの崖の方が日照等の点で不利とみなされ、評価減が大きくなるイメージです。
- 評価額の算出:路線価方式で評価する土地であれば「路線価 × 総面積」で算出した平常時の評価額に上記のがけ地補正率を乗じます。計算式は「(路線価 × 補正率)× 総地積」となり、この結果が崖地補正後の評価額です。例えば、路線価10万円/㎡の地域にある400㎡の土地(平坦なら評価額4億円)で、そのうち100㎡が崖地(割合25%)の場合、崖の向きが南なら補正率0.92なので評価額は約3.68億円に減額されます。同じ条件で崖の向きが北なら補正率0.88となり評価額は3.52億円まで下がります(約4,800万円の減額)。
このように、がけ地補正率の適用による評価減の幅はおおむね「評価額の4%減~最大47%減程度」とされています。補正率の具体的な数値は細かく定められており、崖地割合と方位によって0.96から0.53まで段階的に変化します(※補正率0.96は評価額4%減、0.53は評価額47%減に相当)。つまり、崖部分が土地全体に占める割合が大きく、かつ崖が北向きなど利用上不利な場合ほど評価額の減額幅も大きくなる設計です。
なお、このがけ地補正は路線価方式による評価の場合にのみ適用できます。地方の倍率方式地域(路線価が設定されていない地域)の土地については、そもそも路線価を用いない評価方法のため「がけ地補正率」を直接適用することはありません。倍率方式地域で崖地を評価する場合には、固定資産税評価額等に斜面地の要因が織り込まれているか確認し、不足があれば別途評価下げ要因を検討する必要があります。
評価時の注意点:適用条件・併用不可事項・隣接地との関係

崖地補正を正しく適用するには、いくつか注意すべきポイントがあります。
-
宅地として一体評価される土地が対象
がけ地補正率は、平坦部分と崖部分が一体となった宅地であることが前提です。崖になっている部分の地目(用途区分)が山林や雑種地など宅地以外の場合、それらを別筆の土地として評価する際にはこの補正は使えません。例えば敷地の一部が登記上「山林」となっているケースでは、その部分は宅地造成費控除など別の評価方法を検討することになります。
-
斜面の角度と高さの要件
前述のとおり斜面角度30度以上が一つの基準です。加えて、各自治体の土砂災害指定などでは高さ要件もあります(例えば千葉県の土砂災害警戒区域指定では「高さ5m以上かつ勾配30度以上」が一つの目安)。評価減の適用以前に、安全面から行政上の規制対象となる崖かどうかを確認しておくことも重要です。
-
他の補正との併用
がけ地補正率は路線価に係る他の補正率(奥行価格補正、不整形地補正、間口狭小補正、奥行長大補正など)と併用可能です。例えば崖地かつ不整形な土地であれば、それぞれの要因について所定の補正を行い評価額を減額できます。ただし、後述する宅地造成費控除(造成費相当額の控除)とは重複適用できません。宅地造成費控除は宅地ではない土地(山林や原野等)を宅地に転用する際の造成費見積額を控除する制度であり、既に一体の宅地として評価するケースでは適用対象外となるためです。つまり、崖地補正率による評価減と造成費控除はどちらか一方のみしか使えないという点に注意しましょう。
-
固定資産税評価との混同に注意
市町村が算定する固定資産税評価額でも、崖地について評価が下がる場合があります。しかし相続税評価の「がけ地補正率」と固定資産税評価の減額率は別物です。固定資産税評価で崖部分が安くなっているからといって相続税も自動的に減額されるわけではなく、あくまで相続税の評価計算において別途がけ地補正の適用手続きを踏む必要があります。逆に固定資産税評価では十分減額されていなくても、相続税評価では適切にがけ地補正を適用することで評価額を下げることが可能です。
-
土砂災害特別警戒区域等にある場合
土地が「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」に指定されている場合、相続税評価では「特別警戒区域補正率」という別の減額補正も適用できます。具体的には、崖地補正率による評価額に対してさらに区域補正率(最大で30%の減額)を乗じる形です。区域補正率はその土地のうち特別警戒区域に該当する部分の割合に応じて定められており、たとえば土地の40%以上が特別警戒区域内なら0.8、70%以上なら0.7といった具合です。なお、崖地補正と区域補正を重ねて適用した場合でも、補正率の下限は0.5(評価額50%減)と定められています。千葉県内でも土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定が進んでおり、千葉市内だけでも特別警戒区域が349箇所(令和6年3月時点)にのぼります。該当する土地を相続する場合、これら区域指定も評価や将来の利用に大きく影響します。
-
複数の崖があるケース
敷地内に異なる方向の崖が複数存在する場合、それぞれの崖地部分について面積割合と方位ごとの補正率を算出し、面積加重平均で全体のがけ地補正率を求めます。例えば北向きの崖が○㎡、東向きの崖が○㎡ある場合、それぞれについて補正率を表から取得し、面積比で加重平均した補正率を使うことになります。計算はやや煩雑になるため、専門家に確認してもらうと安心です。
崖地評価でよくある誤解・見落とし・トラブル事例
崖地の評価に関しては、専門家でない方には分かりにくい点も多く、誤解や見落としによるトラブルも起こりがちです。ここでは代表的なケースを紹介します。
-
ケース1:崖地補正の適用漏れによる相続税の過払い
崖地の評価減を知らずに通常通りの評価額で申告してしまい、結果として相続税を過大に納めてしまうケースです。例えば土地を評価する際に崖部分を考慮せず、全て平坦地と同じ価値で計算してしまうと、本来認められるはずの減額を受けられません。後になって専門家に指摘され、更正の請求(払い過ぎた税金の還付請求)手続きを行うケースもあります。相続税の申告期限後5年以内であれば修正が可能な場合もありますが、時間や手間がかかるため、初めから崖地補正を正しく適用しておくことが大切です。
-
ケース2:緩やかな傾斜地なのに大幅な減額を期待してしまう
前述の通り、傾斜が30度未満の場合は原則として「崖地」としての補正は受けられません(代わりに10%減など小幅な調整に留まります)。しかし一般の方には傾斜角の判断は難しく、「見た目に傾いているから大幅に評価が下がるだろう」と思い込んでしまうケースがあります。実際には税務上の基準を満たさず評価減が認められないこともあるため、専門家に現地を見てもらい傾斜度や高さが基準に該当するか確認することが重要です。
-
ケース3:宅地造成費控除と二重に減額しようとする
崖地部分について「がけ地補正率」で評価減をした上で、さらに「宅地造成費」を控除できると誤解するケースです。前述のように、この二つは重複適用できません。造成費控除はあくまで宅地以外の土地を宅地化する場合の評価方法であり、崖地補正とは選択関係になります。二重に減額を主張すると税務署から否認される可能性が高いため注意しましょう。
-
ケース4:固定資産税評価との差異に戸惑う
固定資産税の明細書を見て「崖地評価減」といった項目が載っている場合、「相続税も同じ率で下がるのだろう」と思い込むケースがあります。しかし先述の通り両者は別物です。逆に固定資産税評価では特に減額されていない崖でも、相続税では補正対象となることもあります。この差異を知らないと、相続税評価額の算定でミスをしたり不公平感を覚えたりする原因になります。疑問があれば税理士や資産評価に詳しい専門家に相談し、適切な評価方法を確認しましょう。
-
ケース5:擁壁や境界の管理トラブル
崖地を含む不動産では、隣地との間で擁壁の所有・管理責任をめぐるトラブルが起きることもあります。例えば大雨や地震で擁壁が崩壊し、隣接する敷地に被害が及んだ場合、誰が補修費用を負担するかでもめるケースがあります。相続した崖地に古い擁壁がある場合は事前に安全性を点検し、必要に応じて補強工事を検討することも大切です。また、崖の上端・下端付近は建築制限があるため(多くの自治体で崖から一定距離は建物を建ててはならないといった条例があります)、増改築の計画時に思わぬ制約となることがあります。こうした法規制や安全面の問題も踏まえて総合的に判断する必要があります。
以上のように、崖地に関する評価や管理には専門知識が要求される場面が多々あります。一見すると複雑ですが、誤った認識のまま手続きを進めると思わぬ損失やトラブルにつながる可能性があります。
崖地の売却・買取を検討する際のポイント
相続した崖地について、「手放してしまいたい」「専門の業者に買い取ってもらいたい」と考える方もいるでしょう。しかし崖地の売却(買取)は平坦な土地に比べてハードルが高いのが実情です。崖地がなかなか売れない主な理由として、次のような点が挙げられます。
-
利用方法が限られる
崖地は地形が特殊で地盤も不安定な場合が多く、有効に利用できる部分が限られます。擁壁を築いたり崖から一定距離を離して建物を建てる必要があり、敷地全体を100%活用することが難しくなります。そのため自宅用地として検討する購入希望者に敬遠されがちです。
-
安全性の問題
傾斜が急であればあるほど地滑りや土砂崩れのリスクが高まります。豪雨時の崖崩れや地震による擁壁倒壊など、災害発生時に大きな被害を受ける可能性があり、買主は敬遠する傾向があります。また将来的な擁壁補修など維持費用の不安も付きまといます。
-
造成や建築にコストがかかる
崖地を平坦に近い状態まで造成するには多額の工事費が必要です。不安定な地盤での建築には通常以上に基礎補強や擁壁工事が求められ、建築コストも割高になります。結果として、買主にとっては「購入後にさらにお金がかかる土地」になってしまうため、価格次第では購入を躊躇する原因となります。
-
生活やアクセスの不便さ
高台に位置する崖地は眺望や風通しが良い反面、坂道や階段でのアクセスが必要になることもあります。日常の利便性に難があるため、一般的な住宅用地として人気が下がる傾向があります。
-
法令上の制限
前述したような建築基準法や自治体条例による崖付近の建築制限があり、自由なプランで家を建てられない場合があります。また、急傾斜地崩壊危険区域などに指定されていると開発行為自体に許可が必要となったり、最悪開発不可の場合もあります。こうした法規制の存在も買主にとってはネックになります。
以上の理由から、崖地は買い手が付きにくく、仮に売れるとしても平坦地よりかなり低い価格になりがちです。不動産業者によっては「訳あり物件」として通常より安価に買取りを行うケースもありますが、その際は相場とかけ離れた価格提示になることも覚悟しなければなりません。特に地方の崖地では需要自体が乏しく、買い手探しに時間がかかることも多いでしょう。
千葉県における崖地評価の実務ポイント
千葉県内でも、房総丘陵の縁や台地の斜面などに住宅地が造成され、崖地を含む宅地が各所に見られます。特に印西市・成田市周辺の台地、香取市やいすみ市の海岸沿いの高台、千葉市若葉区・緑区の丘陵地などでは、宅地造成に伴って隣地との高低差が生じているケースがあります。こうした地域では相続税評価の際に崖地補正の適用が検討されるのはもちろん、前述の土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の指定にも注意が必要です。千葉県は台風や豪雨の被害を受けやすく、土砂災害警戒区域の指定数も増加傾向にあります。該当地域の宅地を相続評価する際には、崖地補正と併せて区域補正の適用を検討し、減額漏れがないようにしましょう。
また、千葉県内の実務上、崖地補正の適用については各税務署も一定の知見を持っていますが、評価のための資料準備が重要です。具体的には、宅地造成時の図面や測量図があれば崖部分の範囲を明確に示すことができますし、無い場合でも現地写真や役所のハザードマップ(急傾斜地の場所が示されています)などを用いて「この土地は◯◯㎡が急傾斜地である」ということを説明できるようにすると良いでしょう。場合によっては土地家屋調査士等に依頼して簡易な測量を行い、崖部分の面積を算出するケースもあります。不安がある場合は早めに専門家へ相談し、評価に必要な証拠を揃えておくと安心です。
司法書士法人ふらっとの信頼性・相談体制
相続した不動産に崖地が含まれる場合、その評価や手続には税務・法律双方の知識が要求されます。不安を感じたら、相続手続きの専門家である司法書士等に相談することをおすすめします。千葉県に拠点を置く司法書士法人ふらっとは、成田市・四街道市・柏市に事務所を構え、相続や不動産登記に特化した細やかなサポートを提供している専門家集団です。これまで地域の皆様の相続・遺言相談に数多く対応してきた実績があります。複数名の司法書士が在籍しており、相続分野で高い専門性を有しています。
司法書士法人ふらっとでは、司法書士による相続登記(名義変更)手続きはもちろん、提携税理士や土地家屋調査士とも連携して相続税申告や不動産測量・評価の相談にも対応できる体制を整えています。司法書士法人ふらっとでは初回の無料相談を実施しており、依頼者の不安に寄り添った丁寧なヒアリングを心掛けています。
最後に、相続手続きについて少しでも不安がある方は、ぜひ司法書士法人ふらっとへお気軽にご相談ください。私たちは千葉県内に根ざした専門家として、皆様に安心をお届けすることを第一に考えております。相続税の申告期限は相続発生から10ヶ月と限られていますし、相続登記の義務化(2024年施行)により放置はできない時代です。一人で悩まず、プロの知見を活用して適正かつ有利な手続きを進めましょう。お問い合わせはお電話・メール・LINEで随時受け付けており、初回相談は無料です。不動産の相続に強い司法書士法人ふらっとが、あなたの相続手続きをトータルでサポートいたします。お気軽にご連絡ください。